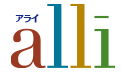BMI(ボディ・マス・インデックス)とは?
BMI(ボディ・マス・インデックス)とは?


BMIは、「Body Mass Index(ボディ・マス・インデックス)」の略称で、身長と体重をもとに、どれくらい肥満しているかを判定するもので、肥満度を表す指標として国際的に用いられています。
自分の肥満度を客観的に把握したい時、「BMI」が手がかりになります。肥満は様々な生活習慣病の引き金となるため、早めに解消することが大切。BMIについて知り、毎日の健康管理に役立てていきましょう。
BMIは、「Body Mass Index(ボディ・マス・インデックス)」の略称で、身長と体重をもとに、どれくらい肥満しているかを判定するもので、肥満度を表す指標として国際的に用いられています。
自分の肥満度を客観的に把握したい時、「BMI」が手がかりになります。肥満は様々な生活習慣病の引き金となるため、早めに解消することが大切。BMIについて知り、毎日の健康管理に役立てていきましょう。
監修
監修


帝京大学理事・名誉教授/臨床研究センターセンター長
寺本内科歯科クリニック内科院長
寺本 民生 先生
帝京大学理事・名誉教授/臨床研究センターセンター長
寺本内科歯科クリニック内科院長
寺本 民生 先生
1973年東京大学医学部卒業、東京大学第一内科入局。茨城県日立総合病院、東京日立病院で内科研修後、東京大学第一内科助手。米国シカゴ大学に留学後、東京大学第一内科医局長、帝京大学内科教授・医学部長を経て、2013年より現職。同年に寺本内科歯科クリニック開業。日本内科学会理事長、日本動脈硬化学会理事長、日本医学会連合副会長、日本専門医機構理事長などを歴任。
1973年東京大学医学部卒業、東京大学第一内科入局。茨城県日立総合病院、東京日立病院で内科研修後、東京大学第一内科助手。米国シカゴ大学に留学後、東京大学第一内科医局長、帝京大学内科教授・医学部長を経て、2013年より現職。同年に寺本内科歯科クリニック開業。日本内科学会理事長、日本動脈硬化学会理事長、日本医学会連合副会長、日本専門医機構理事長などを歴任。
1. BMIって何? どうすれば分かるの?
1. BMIって何? どうすれば分かるの?


■BMIは肥満度を示す国際的な指標
BMIは、体重(kg)を身長(m)の2乗で割ることで求めることができます。この計算方法は、世界共通です。
BMI = 体重(kg) ÷[身長(m)×身長(m)]
例えば身長170cm、体重70㎏の人なら、「BMI = 70÷[1.7×1.7] ≒24.2」という計算でBMIは約24.2になります。身長はセンチメートル(cm)ではなく、メートル(m)で計算するので注意しましょう。
■日本ではBMI25以上を「肥満」と判定
■BMIは肥満度を示す国際的な指標
BMIは、体重(kg)を身長(m)の2乗で割ることで求めることができます。この計算方法は、世界共通です。
BMI = 体重(kg) ÷[身長(m)×身長(m)]
例えば身長170cm、体重70㎏の人なら、「BMI = 70÷[1.7×1.7] ≒24.2」という計算でBMIは約24.2になります。身長はセンチメートル(cm)ではなく、メートル(m)で計算するので注意しましょう。
■日本ではBMI25以上を「肥満」と判定
![BMIの計算式:BMI = 体重(kg) ÷[身長(m)×身長(m)] 日本肥満学会による肥満度判定基準では、BMI18.5未満は低体重(やせ)、BMI18.5~25未満は普通体重、25~30未満は肥満(1度)、30~35未満は肥満(2度)、35~40未満は肥満(3度)、40以上は肥満(4度)と判定され、肥満(3度・4度)は高度肥満に分類されます。](https://taisho.scene7.com/is/image/taisho/012_3?obj=1743665295732&fmt=png-alpha)
![BMIの計算式:BMI = 体重(kg) ÷[身長(m)×身長(m)] 日本肥満学会による肥満度判定基準では、BMI18.5未満は低体重(やせ)、BMI18.5~25未満は普通体重、25~30未満は肥満(1度)、30~35未満は肥満(2度)、35~40未満は肥満(3度)、40以上は肥満(4度)と判定され、肥満(3度・4度)は高度肥満に分類されます。](https://taisho.scene7.com/is/image/taisho/012_3?obj=1743665295732&fmt=png-alpha)
BMIは、その値が高いほど肥満の程度が高いことを示します。ただし、肥満の判定基準は国によって異なります。WHO(世界保健機関)の基準ではBMI = 30以上が「肥満」とされていますが、日本人は欧米人よりも、BMIが高くなくても内臓脂肪の蓄積等により健康被害のリスクが顕在化しやすいことが明らかになっているため、日本肥満学会の基準ではBMI=25以上を「肥満」と定義しています。
さらに、肥満は程度によって「肥満1度」~「肥満4度」に分類され、その中でも特に程度が高い肥満度3~4は「高度肥満」とされています。
BMIは、その値が高いほど肥満の程度が高いことを示します。ただし、肥満の判定基準は国によって異なります。WHO(世界保健機関)の基準ではBMI = 30以上が「肥満」とされていますが、日本人は欧米人よりも、BMIが高くなくても内臓脂肪の蓄積等により健康被害のリスクが顕在化しやすいことが明らかになっているため、日本肥満学会の基準ではBMI=25以上を「肥満」と定義しています。
さらに、肥満は程度によって「肥満1度」~「肥満4度」に分類され、その中でも特に程度が高い肥満度3~4は「高度肥満」とされています。
2. BMIと健康の関係は?
2. BMIと健康の関係は?


■死亡率や有病率が低いのは、BMI=18.5~24.9の「普通体重」
肥満が健康に与える影響については、これまで様々な研究が行われ、BMIとの関係も調査されてきました。BMIと死亡率の関係を死因別・男女別に調べたところ、BMI=18.5~24.9の「普通体重」の人で死亡率、生活習慣病などの有病率・発症率が低く、それ以上でもそれ以下でも健康に対するリスクが高まることが分かりました。
この調査で死亡率や有病率が最も低かったのは、BMI=22の人です。BMI=22といえば、人によっては少しふくよかに思える体型かもしれませんが、統計上ではこの数値の人が最も健康上のリスクが低いと評価されたのです。そのためBMIは22が理想とされ、健康上最適な体重とされる「標準体重」を求める計算式に採用されています。
標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22
例として、身長170cmの場合は、身長の2乗に22を掛けて、標準体重は63.58㎏ということになります。どのくらいの体重が適正なのかを判断する際はこの標準体重を目安にし、上下10%以内の体重を目標にするとよいでしょう。
■BMI=25以上の「肥満」は、生活習慣病に注意が必要
■死亡率や有病率が低いのは、BMI=18.5~24.9の「普通体重」
肥満が健康に与える影響については、これまで様々な研究が行われ、BMIとの関係も調査されてきました。BMIと死亡率の関係を死因別・男女別に調べたところ、BMI=18.5~24.9の「普通体重」の人で死亡率、生活習慣病などの有病率・発症率が低く、それ以上でもそれ以下でも健康に対するリスクが高まることが分かりました。
この調査で死亡率や有病率が最も低かったのは、BMI=22の人です。BMI=22といえば、人によっては少しふくよかに思える体型かもしれませんが、統計上ではこの数値の人が最も健康上のリスクが低いと評価されたのです。そのためBMIは22が理想とされ、健康上最適な体重とされる「標準体重」を求める計算式に採用されています。
標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22
例として、身長170cmの場合は、身長の2乗に22を掛けて、標準体重は63.58㎏ということになります。どのくらいの体重が適正なのかを判断する際はこの標準体重を目安にし、上下10%以内の体重を目標にするとよいでしょう。
■BMI=25以上の「肥満」は、生活習慣病に注意が必要


BMI=25以上の「肥満」であっても比較的軽度の肥満の場合は、直ちに健康上の問題があるとは言えません。ただし、BMI判定での「肥満」に加えて、「腹囲(=ウエスト周囲長)」も基準値を超えている場合は「内臓脂肪型肥満」である可能性が高く、生活習慣病のリスクが高くなります。
内臓脂肪型肥満は、お腹の内臓の周りに脂肪がつくタイプの肥満で、男性や閉経後の女性に多く見られるものです。内臓脂肪型肥満では、血圧や血糖値、中性脂肪値が上がりやすくなったり、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が悪化し、そのために血管の老化である動脈硬化が進みやすくなったりすることが分かっています。その結果、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が悪化し、動脈硬化が進めば、脳梗塞や心筋梗塞など命にかかわる病気を招くリスクが高まってしまいます。
日本人は肥満3度以上の高度肥満の人は少なく、ほとんどが「軽度肥満」に該当しますが、肥満1度であっても糖尿病、脂質異常症、高血圧などの人が多いため注意が必要です。このように肥満に伴う合併症や内臓脂肪の蓄積が認められる場合は、単なる肥満ではなく「肥満症」と呼ばれ、治療の対象となります。
肥満度3~4の「高度肥満」で内臓脂肪の蓄積が認められる場合は、合併症の有無にかかわらず、「肥満症」と診断されます。現状ではこれといった症状がなくても、放置すれば将来的に様々な病気や不調を招くリスクが高いため、該当する人は早めに医療機関で食事・運動の指導や治療を受け、肥満の解消に努めることが大切です。
<肥満が原因で起こる病気>
●糖尿病 ●脂質異常症 ●高血圧 ●高尿酸血症、痛風 ●脳梗塞 ●狭心症、心筋梗塞 ●脂肪肝 ●睡眠時無呼吸症候群 ●月経異常 ●変形性関節症 ●腰痛症 など
■BMI=18.5未満の「低体重(やせ)」にもリスクが
BMI=25以上の「肥満」であっても比較的軽度の肥満の場合は、直ちに健康上の問題があるとは言えません。ただし、BMI判定での「肥満」に加えて、「腹囲(=ウエスト周囲長)」も基準値を超えている場合は「内臓脂肪型肥満」である可能性が高く、生活習慣病のリスクが高くなります。
内臓脂肪型肥満は、お腹の内臓の周りに脂肪がつくタイプの肥満で、男性や閉経後の女性に多く見られるものです。内臓脂肪型肥満では、血圧や血糖値、中性脂肪値が上がりやすくなったり、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が悪化し、そのために血管の老化である動脈硬化が進みやすくなったりすることが分かっています。その結果、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が悪化し、動脈硬化が進めば、脳梗塞や心筋梗塞など命にかかわる病気を招くリスクが高まってしまいます。
日本人は肥満3度以上の高度肥満の人は少なく、ほとんどが「軽度肥満」に該当しますが、肥満1度であっても糖尿病、脂質異常症、高血圧などの人が多いため注意が必要です。このように肥満に伴う合併症や内臓脂肪の蓄積が認められる場合は、単なる肥満ではなく「肥満症」と呼ばれ、治療の対象となります。
肥満度3~4の「高度肥満」で内臓脂肪の蓄積が認められる場合は、合併症の有無にかかわらず、「肥満症」と診断されます。現状ではこれといった症状がなくても、放置すれば将来的に様々な病気や不調を招くリスクが高いため、該当する人は早めに医療機関で食事・運動の指導や治療を受け、肥満の解消に努めることが大切です。
<肥満が原因で起こる病気>
●糖尿病 ●脂質異常症 ●高血圧 ●高尿酸血症、痛風 ●脳梗塞 ●狭心症、心筋梗塞 ●脂肪肝 ●睡眠時無呼吸症候群 ●月経異常 ●変形性関節症 ●腰痛症 など
■BMI=18.5未満の「低体重(やせ)」にもリスクが


BMIと死亡率の調査では、肥満度1程度の軽い肥満の人よりも、BMI=18.5未満の「低体重(やせ)」の人のほうが、死亡率が高いことが分かりました。低体重のリスクとしては、栄養不足による骨粗鬆症や貧血、月経異常、妊娠合併症、不整脈、免疫力の低下による感染症、がんなどが指摘されています。また、高齢期の低体重はフレイル(※)につながりやすく、健康寿命にも影響するため注意が必要です。低体重に該当する人は、必要な栄養素やエネルギーを不足なく摂れているか見直すようにしましょう。
※フレイル…日本語の「虚弱」に当たる言葉で、高齢期に身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のこと。低栄養から筋力や筋肉量が減少して体重が減り、転倒や骨折、慢性疾患の悪化などをきっかけに要介護状態になる可能性が高い。
BMIと死亡率の調査では、肥満度1程度の軽い肥満の人よりも、BMI=18.5未満の「低体重(やせ)」の人のほうが、死亡率が高いことが分かりました。低体重のリスクとしては、栄養不足による骨粗鬆症や貧血、月経異常、妊娠合併症、不整脈、免疫力の低下による感染症、がんなどが指摘されています。また、高齢期の低体重はフレイル(※)につながりやすく、健康寿命にも影響するため注意が必要です。低体重に該当する人は、必要な栄養素やエネルギーを不足なく摂れているか見直すようにしましょう。
※フレイル…日本語の「虚弱」に当たる言葉で、高齢期に身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のこと。低栄養から筋力や筋肉量が減少して体重が減り、転倒や骨折、慢性疾患の悪化などをきっかけに要介護状態になる可能性が高い。
3. BMIにも限界あり! 他の指標と組み合わせよう
3. BMIにも限界あり! 他の指標と組み合わせよう


■BMIが必ずしも健康状態を完全に反映するわけではない
肥満度の指標となるBMIですが、BMIだけで肥満の有無や健康リスクを判断するのが難しい場合があります。例えばアスリートは、BMIが高くても健康的な場合が少なくありません。筋肉量が多い人はその分体重も重く、BMIが高く出やすい傾向が見られます。
逆にBMIで「肥満」とされるレベルに達していなくても、内臓脂肪型肥満が進んでいるケースもあります。BMIだけでは体重の中身までは分からないのです。その意味でも、BMIだけで健康状態を判断するのは完全とはいえません。
■BMIと一緒にチェックすべき他の指標とは?
現在、医療機関などで行われている肥満の判定方法には、BMIの他に「体脂肪率」と「腹囲(ウエスト周囲長)」があります。それぞれ一長一短があるので、これらを組み合わせてより正確な健康評価を行いましょう。
体脂肪率
■BMIが必ずしも健康状態を完全に反映するわけではない
肥満度の指標となるBMIですが、BMIだけで肥満の有無や健康リスクを判断するのが難しい場合があります。例えばアスリートは、BMIが高くても健康的な場合が少なくありません。筋肉量が多い人はその分体重も重く、BMIが高く出やすい傾向が見られます。
逆にBMIで「肥満」とされるレベルに達していなくても、内臓脂肪型肥満が進んでいるケースもあります。BMIだけでは体重の中身までは分からないのです。その意味でも、BMIだけで健康状態を判断するのは完全とはいえません。
■BMIと一緒にチェックすべき他の指標とは?
現在、医療機関などで行われている肥満の判定方法には、BMIの他に「体脂肪率」と「腹囲(ウエスト周囲長)」があります。それぞれ一長一短があるので、これらを組み合わせてより正確な健康評価を行いましょう。
体脂肪率


肥満とは、体の中の脂肪が必要以上に増えた状態です。体脂肪率は体重に占める体脂肪の割合をいい、体型と関係なく脂肪が増え過ぎているかどうかを知ることができます。一般に、健康的とされる体脂肪率の目安は男性10〜19%、女性20〜29%で、男性は20%以上、女性は30%以上の場合に「肥満」と判定されます。
正確な測定のためには医療用の精密な測定器が必要ですが、家庭用の測定器(※)でおおよその体脂肪率を知ることができます。家庭で測る場合は、メーカーによって測定値が多少異なること、体が濡れている状態で測ると数値が低く出やすいことに留意し、できるだけ同じ条件で測って数値の変化を見るようにしましょう。
※体重計で体脂肪率測定機能がついているものや、両手でバーを握って測るものなど
<体脂肪率による肥満の判定基準>
成人男性
20~25%未満…軽度肥満
25~30%未満…中等度肥満
30%以上…高度肥満
成人女性
30~35%未満…軽度肥満
35~40%未満…中等度肥満
40%以上…高度肥満
腹囲(ウエスト周囲長)
肥満とは、体の中の脂肪が必要以上に増えた状態です。体脂肪率は体重に占める体脂肪の割合をいい、体型と関係なく脂肪が増え過ぎているかどうかを知ることができます。一般に、健康的とされる体脂肪率の目安は男性10〜19%、女性20〜29%で、男性は20%以上、女性は30%以上の場合に「肥満」と判定されます。
正確な測定のためには医療用の精密な測定器が必要ですが、家庭用の測定器(※)でおおよその体脂肪率を知ることができます。家庭で測る場合は、メーカーによって測定値が多少異なること、体が濡れている状態で測ると数値が低く出やすいことに留意し、できるだけ同じ条件で測って数値の変化を見るようにしましょう。
※体重計で体脂肪率測定機能がついているものや、両手でバーを握って測るものなど
<体脂肪率による肥満の判定基準>
成人男性
20~25%未満…軽度肥満
25~30%未満…中等度肥満
30%以上…高度肥満
成人女性
30~35%未満…軽度肥満
35~40%未満…中等度肥満
40%以上…高度肥満
腹囲(ウエスト周囲長)


腹囲はおへその高さで測ったウエスト周囲長をいいます。内臓脂肪の蓄積を知るために重要な指標で、メタボリックシンドロームの診断に欠かせません。腹囲が基準値を超える場合は、生活習慣病のリスクの高い「内臓脂肪型肥満」が強く疑われます。
家庭でもメジャーがあれば簡単に測定できますが、その際はウエストのくびれた部分ではなく、「おへその高さ」で床と水平にメジャーを当てて測るのが大切なポイントです。食後を避けて空腹時に、できるだけ同じ条件で行うようにしましょう。
<腹囲の基準値>
男性85cm未満 女性90cm未満
腹囲はおへその高さで測ったウエスト周囲長をいいます。内臓脂肪の蓄積を知るために重要な指標で、メタボリックシンドロームの診断に欠かせません。腹囲が基準値を超える場合は、生活習慣病のリスクの高い「内臓脂肪型肥満」が強く疑われます。
家庭でもメジャーがあれば簡単に測定できますが、その際はウエストのくびれた部分ではなく、「おへその高さ」で床と水平にメジャーを当てて測るのが大切なポイントです。食後を避けて空腹時に、できるだけ同じ条件で行うようにしましょう。
<腹囲の基準値>
男性85cm未満 女性90cm未満
4. まとめ
4. まとめ
BMIは肥満の判定に用いられる基本的な指標です。BMIをベースにしつつ体脂肪率や腹囲もチェックして、健康状態を判断するための目安にしましょう。測定値が基準を超えている場合は、必要に応じて生活習慣の見直しや医療機関の受診を検討してください。
BMIは肥満の判定に用いられる基本的な指標です。BMIをベースにしつつ体脂肪率や腹囲もチェックして、健康状態を判断するための目安にしましょう。測定値が基準を超えている場合は、必要に応じて生活習慣の見直しや医療機関の受診を検討してください。
 製品情報サイト
製品情報サイト